ヘッドライン
-
更新案内
26/1/30
お知らせ情報を1件更新しました。25/12/26
お知らせ情報を1件更新しました。
新作コンテンツを公開しました。25/9/25
お知らせ情報を1件更新しました。
その他に微修正を行いました。 -
新作コンテンツ
-
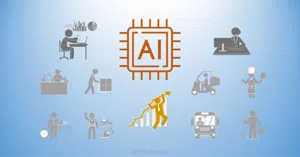
AI活用で加速する中小企業の成長と価値創造
公開2025/12/26
中小企業が課題を解決して事業継続を図るには、経営戦略に基づくAI導入により、段階的な成長と価値創造を実現することが不可欠です。
-
IT活用コンサルタント『ICTイノベート』は手軽で実用的なIT活用を安価な仕組みで実践します。企業経営における目標達成や課題解決をIT活用により支援します。
26/1/30
お知らせ情報を1件更新しました。
25/12/26
お知らせ情報を1件更新しました。
新作コンテンツを公開しました。
25/9/25
お知らせ情報を1件更新しました。
その他に微修正を行いました。
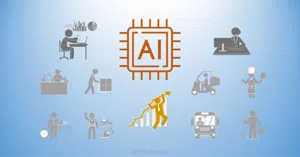
公開2025/12/26
中小企業が課題を解決して事業継続を図るには、経営戦略に基づくAI導入により、段階的な成長と価値創造を実現することが不可欠です。
情報処理推進機構(IPA)から「情報セキュリティ10大脅威 2026」が公開されました。(1/29付)
これらは、2025年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から選出されており、「組織」の立場と「個人」の立場での10大脅威が公開されています。
「組織」向け脅威は従来通り順位形式になっていますが、「個人」向け脅威は順位ではなく五十音順に並べられています。
IPAによれば、「順位が高い脅威から優先的に対応し、下位の脅威への対応が疎かになることを懸念してのことであり、順位に関わらず自身に関係のある脅威に対して対策を行うことを期待する」とのことです。
「組織」向け脅威の順位では、1位「ランサム攻撃による被害」と2位「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」は前回と変わりませんでした。
2025年もランサムウェアに感染した企業・組織が多く確認され、取引先を含むサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼしたニュースを多く目にしました。こうした情勢がランキングにも反映されていることがうかがえます。
また、3位「AIの利用をめぐるサイバーリスク」は、今回初選出で上位にランクインしました。想定されるリスクは多岐にわたります。
・AIに対する不十分な理解に起因する意図しない情報漏えい
・他者の権利侵害といった問題
・AIが加工・生成した結果を十分に検証せず鵜呑みにすることにより生じる問題
・AIの悪用によるサイバー攻撃の容易化、手口の巧妙化
などが挙げられます。上位にランクインした背景には、こうしたリスクの存在があると考えられます。
最新の脅威情報を理解することにより、効果的なセキュリティ対策を行うことが可能となります。
各脅威が自環境に対してどのようなリスクがあるのか洗い出すことが重要です。そして、セキュリティ対策情報を継続的に収集し、使用している機器やサービスに適切なセキュリティ対策を講じましょう。
今後の予定として、「情報セキュリティ10大脅威 2026」に選出された各脅威の手口、傾向や対策などの詳しい解説資料が、2月末に公開予定とされています。
また、公開済コラムに情報反映しました。
「中小企業向けAI活用ガイド~生成AIを中心としたAIの戦略的導入~」は、ITコーディネータ協会(ITCA)によって策定されました。
本ガイドは、現在の日本経済が直面する深刻な人手不足、急速な市場変動、グローバル化、そしてデジタル化という二重三重の構造的課題に対し、中小企業が持続的な競争優位性を確保し、事業継続を図るために策定されました。
その狙いは、AI導入を単なるIT技術導入として扱うのではなく、ビジネスモデル変革を支える経営戦略として位置づけ、その体系的なフレームワークを構築することにあります。これにより、経営者、DX推進担当者、支援者などのステークホルダー間の認識のズレを防ぎ、効果的なAI活用プロジェクトの推進を可能にします。
AI活用がもたらす影響は、業務効率化や定型業務の自動化による生産性向上に留まらず、新たな収益機会の創出や組織力・人材価値の向上など、企業経営の根幹に及びます,。特に、限られた経営資源(人手や予算)で成果を最大化し、大企業との情報格差を解消したい中小企業にとって、AI導入は必須の経営課題であります。
本ガイドは、ITコーディネータがAI活用の支援を行う実践的な指針となる一方で、中小企業の経営者・役員、DX推進の担当者、自治体・支援機関の担当者など、幅広い読者層に向けて構成されています。技術的な専門知識を持たない担当者でも、AI活用のために必要とされる考慮事項を体系的に学ぶことができ、限られた経営資源の中で最適な投資判断を行うための客観的な評価軸と導入プロセスを提供します。
本ガイドを活用することで、中小企業はAI活用に伴う不確実性をマネジメントし、持続的な価値を創出するための確かな道標を得ることができます。
本ガイドは、ITCAの公式サイト(生成AI研究会のページ)でWeb版を閲覧することが可能となっています(無料)。
また、当サイトでは本ガイドの内容を整理したコラム記事を作成しましたので、宜しければご覧ください。
情報処理推進機構(IPA)から「情報セキュリティ白書2025 一変する日常:支える仕組みを共に築こう」が発行されました。PDF版が9/10に公開され、書籍版は9/30に刊行されます。
本白書は2008年以来、サイバーセキュリティの脅威や政策の動向をまとめた年次報告書です。
2024年度、サイバー空間の脅威は一層深刻化しました。国内では大手企業がランサムウェア攻撃によりサービスの長期停止に追い込まれるなど、社会・経済活動に大きな影響が出ています。
攻撃手口も、取引先などサプライチェーンの脆弱な部分を狙うものや、生成AIを悪用して偽情報を生成するものなど、ますます高度化・巧妙化しています。さらに、厳しい国際情勢を背景に、重要インフラを標的とした攻撃や国家が支援するグループによる情報窃取活動も顕在化し、安全保障上の課題となっています。
こうした状況を受け、国内の政策も強化されています。攻撃の兆候を事前に探知し被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に向けた法整備が進められました。また、設計段階からセキュリティを組み込む「セキュア・バイ・デザイン」の考えに基づき、SBOM(ソフトウェア部品表)の導入推進や、IoT製品のセキュリティ認証制度「JC-STAR」の運用が開始されるなど、社会全体のサイバーリスク耐性を高める取り組みが進んでいます。
本白書は、これらの2024年度の情勢を踏まえた脅威分析と政策動向を総括し、以下の構成で多角的に解説しています。
・序章:2024年度の情報セキュリティの概況
・第1章:国内外のサイバー脅威の動向
・第2章:最近のサイバー空間を巡る注目事象(AIセーフティ、偽・誤情報の脅威など)
・第3章:国内の政策及び取り組みの動向
・第4章:国際的な政策及び取り組みの動向
本白書は、最新の脅威動向から国内外の政策までを網羅した情報を提供しています。サイバーセキュリティに関わる最新状況の把握と、それに伴う脅威やリスクに対する備えを実践するために、本白書を活用されては如何でしょうか。
なお、本白書のPDF版については、アンケートに回答すればダウンロードして無料で入手することが可能となっています。
警察庁は、サイバー犯罪対策の一環として、ランサムウェア「Phobos/8Base」によって暗号化された被害データを復号するツールの開発を公表しました。(7/17付)
同庁のウェブサイトで「復号ツール」や「利用ガイドライン」が公開されており、誰でもダウンロードして利用が可能とのことです。
また同庁では、ランサムウェアの被害に遭った国内の企業などに対して相談を促しており、希望に応じて復号ツールを活用して被害回復作業を実施することとしています。
こうした同庁の取り組みは、国際的な共同プロジェクトである「No More Ransom」とも連携しています。同プロジェクトは、サイバー犯罪者に不当な身代金を支払うことなく、ロックされた端末や暗号化されたデータを取り戻すための支援を提供しており、「身代金を支払ってもデータを取り戻せる保証はないため、絶対に支払ってはいけません」と強く警告しています。
ランサムウェアの脅威は、組織にとって最も深刻なサイバー脅威の一つとなっています。情報処理推進機構(IPA)が毎年公表する「情報セキュリティ10大脅威(組織編)」では、長きにわたって第1位に挙げられています。(2021年版から2025年版の5回連続)
ランサムウェアの被害は、単にデータを暗号化するだけでなく、窃取したデータを公開すると脅迫する「二重恐喝(ダブルエクストーション)」や、データを暗号化せずに窃取のみを行う「ノーウェアランサム」といった手口も確認されており、その手口は巧妙化しています。
同庁では、このような状況を受け、「ランサムウェア被害防止対策」としてランサムウェアの被害を未然に防ぐための包括的な対策も強く呼びかけています。
警察庁の取り組みは、復号ツールの提供のみならず、国際的な連携、そして詳細な予防策の提示を通じて、サイバー空間におけるランサムウェアの脅威から利用者を守るための多角的なアプローチを推進していることをご紹介しました。
情報処理推進機構(IPA)では、DXの取組とその成果について調査した結果をまとめた「DX白書2021」「DX白書2023」「DX動向2024」に続き、「DX動向2025」を公開しました。(6/26付)
「DX動向2025 ~日米独比較で探る成果創出の方向性「内向き・部分最適」から「外向き・全体最適」へ~」では、これまでの日本企業の動向分析に加え、新たに米国・ドイツの企業との比較を通じて、日本企業の現在地と今後の課題を多角的に明らかにしています。
調査期間は、2025年2月から3月にかけて実施されています。調査項目は「戦略」「技術」「人材」という3つの視点から成り、本報告書では以下の3つの軸で分析を行っています。
1.DXの取組と成果の状況
2.DX実現に向けた技術利活用の状況
3.DXを推進する人材の状況
ビジネスパーソン、情報システム部門、DX推進部門などを対象に、日米独3カ国の比較を通じて、それぞれの国のDXの「今」が浮き彫りになっています。
目立った調査結果をピックアップします。
・DX成果の低さ:DXから「成果が出ている」と回答した割合は、米国とドイツは8割を超えているのに対し、日本は6割弱と低くなっています。
・成果創出の方向性: 日本は「コスト削減」「製品・サービス等提供にかかる日数削減」といった生産性向上や業務効率化のような内向きの取組みに関する成果が多い傾向にあるのに対し、米国やドイツは「売上高増加」「利益増加」「市場シェア向上」「顧客満足度」といったバリューアップを中心とした外向きの取組みに関する成果が多い傾向があることが分かりました。
・成果指標設定の不足:日本企業でDXの成果を把握するための指標を設定している割合は3割以下でしたが、米国とドイツは共に8割以上となっており、指標の設定において大きな差が見られました。
・DX人材の深刻な不足:DXを推進する人材が「不足している」と回答した日本企業の割合は8割を超えており、一方で米国とドイツにおいては「やや過剰である」「過不足はない」の回答割合の合計がそれぞれ7割と5割程度となっています。日本は他国と比較して人材不足が深刻化していることが示されています。
今回の「DX動向2025」は、日本企業がDX推進における現状課題を理解し、今後の戦略立案に役立つ貴重な情報源となります。
本報告書は無料でPDFファイルを入手できます。また、IPAでは本報告書についての参加無料のオンライン説明会を予定しているようです。
中小企業基盤整備機構(中小機構)では、デジタル化を後押しするためのポータルサイト「デジwith」をオープンしました。(4/1付)
これまでの「みらデジ」が3月末で終了し、新サービスとして「デジwith」が提供されました。登録不要で、誰でも利用可能とのことです。
「デジwith」は、事業者(中小企業・小規模事業者)へ、デジタル化に取り組むきっかけ作りから課題の設定、解決のための最適なITソリューションの提案・導入・運用までを一貫してサポートするポータルサイトです。
中小企業のDX推進に関する調査(2024年中小機構)によると、DXの取組が「必要だと思うが取り組めていない」実態が、事業者の規模が小さくなるほど顕著になる結果が出ており、特に小規模事業者においては、デジタル化に取り組むきっかけがないこと、何から始めればよいかわからないことがネックとなっているとのことです。
このような背景から、デジタル化に取り組むきっかけ作りから道筋を示し、最適なITソリューションの提案、導入・運用までを一貫してサポートすることを目的として、「デジwith」をオープンしたとのことです。
以下のような様々なメニューにより、事業者のデジタル化をサポートするとのことです。
1.同業他社とデジタル化状況を比較し、経営の悩みを解決するITソリューションを知る「IT戦略ナビwith」
2.具体的な業務用アプリやIT導入事例を探す「ここからアプリ」
3.ITの専門家へオンライン相談できる「IT経営サポートセンター」
また、当サイトの「お役立ちサイト」においても、「みらデジ」から「デジwith」に差し替えました。
情報処理推進機構(IPA)では企業向けに、セキュリティインシデント発生時、及び平時に実施すべき対策等についての相談窓口を開設しました。(4/1付)
以下のような相談内容への活用を想定しているとのことです。(引用)
〇各種インシデント発生時の初動対応に関する相談
・起きている事象をヒアリングして、被害が発生しているか否かを判断します。
・被害が発生している場合、有効な応急処置についてご案内します。
・インシデント対応を行う専門業者一覧の紹介をします。
・他に必要な相談・報告先等の紹介をします。
ご相談いただく事案の調査や解析の実施は対応しておりません。
〇標的型サイバー攻撃に関するインシデント相談
・国家支援型と推定される標的型サイバー攻撃(APT)を受けた場合は、専門的知見をもとに支援を実施します。
〇その他の情報セキュリティに関する一般的な相談
・中小企業などにおける、情報セキュリティ対策ガイドラインや各種支援ツール・支援施策などをご案内します。
〇脅威情報に関する情報提供
・IPAによる被害拡大防止策の実施や注意喚起のために、標的型サイバー攻撃や、その他の脅威情報に関して情報提供を受け付けています。必要に応じて折り返しご連絡する場合がございます。
なお、相談方法はメール問い合わせになるようです。
情報処理推進機構(IPA)から「2024年度中小企業等実態調査結果」の速報版が公開されました。(2/14付)
近年、サプライチェーンを狙った高度なサイバー攻撃が増加しており、中小企業が標的となるケースが多くなっています。サプライチェーン全体でのセキュリティ対策の必要性が高まっています。
IPAでは、中小企業等における情報セキュリティ対策の実態を明らかにする目的から、「中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」を実施してきました。これまで2016年度と2021年度に実施されており、今回は後続となる調査です。
なお、2/14付で公開されたのは「速報版」であり、詳細な報告書は4月頃にIPAのウェブサイトで公開予定とのことです。
本調査は、全国の中小企業を対象にウェブアンケートを行い、自社や取引先を含むセキュリティ対策の状況をはじめ、被害や課題について調査しており、4191社から回答を得ています。
その結果、前回(2021年度調査)と比べて情報セキュリティ対策の実施状況の改善はわずかであり、更なる対策の必要性の訴求や対策の実践に向けた支援の必要性が明らかになっています。主なポイントは以下のとおりです。
1.過去3期内で、サイバーインシデントが発生した企業における被害額の平均は73万円(うち9.4%は100万円以上)、復旧までに要した期間の平均は5.8日(うち2.1%は50日以上)
2.不正アクセスされた企業の約5割が脆弱性を突かれ、他社経由での侵入も約2割
3.サイバーインシデントにより取引先に影響があった企業は約7割
4.約7割の企業が組織的なセキュリティ体制が整備されていない
5.過去3期における情報セキュリティ対策投資を行っていない企業は約6割
6.情報セキュリティ関連製品やサービスの導入状況は微増
7.セキュリティ対策投資を行っている企業の約5割が、取引につながった
8.サイバーセキュリティお助け隊サービスの導入企業の5割以上が、セキュリティ対策の導入が容易と回答し、また3割以上の企業が費用対効果を実感している
こうして見ると、個社の情報セキュリティ対策の不備がサイバーインシデントを引き起こすだけでなく、サプライチェーン全体での情報セキュリティの不備が、取引先にも深刻な影響を及ぼしていることが明らかになっています。
こうした実態の分析に加えて、中小企業の情報セキュリティ対策に役立つ「サイバーセキュリティお助け隊サービス」についても触れられています。
情報セキュリティの認識を向上させ、情報セキュリティ対策を進める上で参考になると思われますので、本調査に目を通されてはいかがでしょうか。
企業経営における目標達成・課題解決をIT活用により支援する IT活用コンサルタント『ICTイノベート』の情報発信サイトです。
何かご不明の点がございましたら、下のメールアドレスまでご連絡頂ければ幸いです。(●は@(半角)に置換)
front●ictinnovate.jp